
歯科衛生士は、全国どこでも活躍できる国家資格として、安定した将来性と高い専門性を兼ね備えた職業です。
結婚や転居などライフステージの変化があっても、働く場所を選びやすいのが大きな魅力で、求人倍率が非常に高いため就職や再就職にも困りません。
一方で、医療現場ならではの感染症リスクや少人数の職場ゆえの人間関係の難しさなど、デメリットがある点には注意が必要です。
この記事では、歯科衛生士として働くメリットとデメリット、歯科衛生士になる方法や具体的な仕事内容について詳しく紹介します。
歯科衛生士として働く6つのメリット

歯科衛生士は、安定した需要と高い専門性を持つ魅力的な職業です。ここでは、具体的な6つのメリットを詳しく解説します。
求人数が多く全国どこでも働ける
歯科衛生士は、全国の歯科医院や病院、保健センターなど幅広い職場で求められているため、求人数が非常に多い職業です。
全国歯科衛生士教育協議会の「歯科衛生士教育に関する現状調査の結果報告」によると、2022年度の就職者に対する求人倍率は23.3倍と高水準です。
つまり、1人の歯科衛生士を20以上の歯科医院が取り合うような状態で、求職者側が職場を選びやすく、どの地域でも安定して仕事を見つけやすい環境が整っています。
国家資格であるため、転居やライフステージの変化があっても、全国どこでも資格を活かして働けるでしょう。
就職や転職の際に選択肢が多く、安定したキャリア形成ができる点は大きなメリットで、需要の高さが将来性の裏付けにもなっています。
ワークライフバランスの実現
歯科衛生士は、勤務時間が比較的規則的で夜勤がほとんどありません。
多くの歯科医院では9時から19時ごろまでの勤務が一般的で、週休2日制を採用している職場も多くあります。
予約制診療が中心のため残業が発生しにくく、プライベートの時間を確保しやすい点が特徴です。
また、パートやアルバイトなど多様な雇用形態が選べるため、ライフスタイルや家庭の事情に合わせて働き方を柔軟に調整できます。
仕事と生活のバランスを重視したい方にとって、非常に魅力的な職業です。
結婚・出産後も続けられる
歯科衛生士は、結婚や出産などのライフイベントを経ても働き続けやすい職業です。
国家資格のため、一度離職しても再就職や復職がしやすく、年齢やブランクが大きな障害になりにくい特徴があります。
実際に多くの女性歯科衛生士が、育児や家庭と両立しながらパート勤務や時短勤務で現場に復帰しています。
専門性が高く即戦力として求められるため、ライフステージに合わせて柔軟に働き方を選べる点は、長期的なキャリア形成を目指す方にとって大きな強みです。
高いやりがいと社会貢献性
歯科衛生士は、患者さんの口腔健康を守ることで生活の質向上に直接貢献できる仕事です。
専門知識と技術を活かし、虫歯や歯周病の予防、口腔ケア指導などを通じて、幅広い世代の健康を支えます。
保育園や高齢者施設、被災地など活躍の場も多岐にわたり、社会的な役割の大きさを実感できます。
また、患者さんからの感謝の言葉や笑顔に触れる機会も多く、やりがいを感じやすい点も特徴です。社会貢献を重視したい方にとって、非常に魅力的な職業といえます。
安定した給与と待遇
歯科衛生士は、医療分野の専門職として安定した収入が見込めます。
歯科衛生士の平均年収は、2024年時点で全国平均約405万円とされています。(参考:厚生労働省)
景気や社会情勢の影響を受けにくいため、長期的に安定した生活基盤を築きやすい点がメリットです。
また、昇給や賞与が支給される職場も多く、経験やスキルの向上に応じて収入アップも期待できます。
キャリアアップの機会
歯科衛生士は、専門性を高めるための研修や認定資格が充実しており、キャリアアップの道が多彩に用意されています。
例えば、予防歯科や訪問歯科、摂食嚥下リハビリテーションなど、専門分野でのスキルを磨くことで、より高度な業務や管理職へのステップアップが可能です。
日本歯科衛生士会などが主催する研修や認定制度を活用すれば、知識や技術の幅を広げられます。
自分の志向やライフプランに合わせて成長できる環境が整っている点も、歯科衛生士の大きな魅力です。
歯科衛生士として働く3つのデメリット

多くのメリットがある歯科衛生士ですが、見過ごせないデメリットも存在します。ここでは、主な3つのデメリットを具体的に解説します。
人間関係のトラブルが起こりやすい
歯科衛生士の職場はスタッフ同士の距離が近く、院長や先輩、後輩との関係が仕事の満足度に大きく影響します。
狭い職場環境や少人数体制のため、ちょっとしたすれ違いがストレスやトラブルにつながりやすいのが実情です。
人間関係の悪化は、仕事のやりがいやモチベーションの低下、さらには離職の原因にもなります。
毎日顔を合わせるメンバーとの関係が円滑でないと、職場に行くのが億劫になりやすいです。
人間関係の悩みは歯科衛生士の離職理由でも上位に挙げられており、働き続ける上で大きな課題となっています。
感染症リスク
歯科衛生士は患者さんの口腔内に直接触れるため、感染リスクが高い職業です。
特にウイルスや細菌が唾液や血液を介して感染する可能性があるため、日々の業務で細心の注意が必要です。
標準予防策を徹底していれば感染リスクは低減できますが、油断や設備の不備があるとリスクが高まります。
厚生労働省や各種調査でも、歯科衛生士は他の医療職種と比べても感染リスクが高い職業と位置づけられています。
安全な職場環境を維持するためにも、常に最新の感染対策を意識し続けましょう。
常に勉強が必要
歯科衛生士は、医療技術や知識が日々進歩する分野で働くため、常に自己研鑽が求められます。
新しい治療法や機器、予防技術などが次々と導入されるため、最新情報の収集や技術習得は欠かせません。
業務の合間や休日にセミナーや研修へ参加し、専門書で学ぶ必要があるため、時間的・精神的な負担を感じやすいです。
知識や技術のアップデートを怠ると、現場での信頼や評価に影響するため、継続的な学習が歯科衛生士の重要な課題となっています。
歯科衛生士になる方法
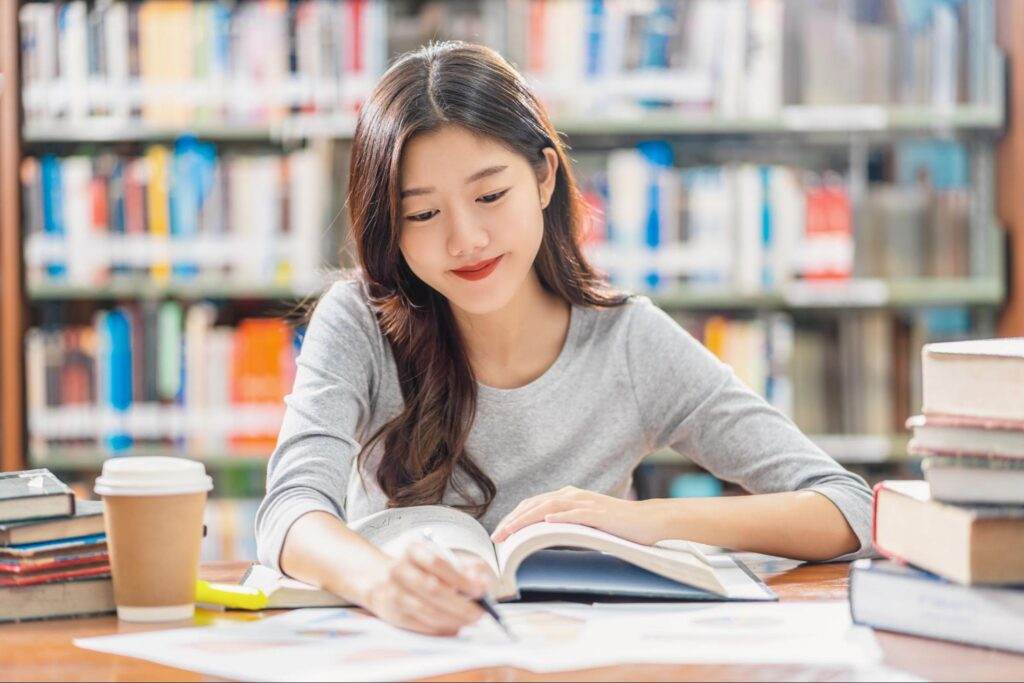
歯科衛生士として働くためには、国家資格の取得とその後の就職活動が必要です。ここでは、歯科衛生士になるための3つのステップを詳しく解説します。
高校を卒業後に養成機関で3年以上学ぶ
歯科衛生士を目指すには、高校を卒業後、厚生労働省や文部科学省が指定した養成機関で3年以上学ぶ必要があります。
養成機関には以下の3つの選択肢があります。
- 専門学校:実践的なカリキュラムが中心で、即戦力となる技術を効率よく学習
- 短期大学:教養科目も学びつつ、3年間で准学士の資格も取得
- 4年制大学:学士の資格が得られ、より高度な専門知識や研究能力を習得
養成機関では、歯科衛生士として必要な専門知識と技術を段階的に身につけます。学習内容は主に以下の通りです。
- 歯科予防処置
- 歯科診療補助
- 歯科保健指導
これら3つの業務に関する知識と技術を中心に学び、口腔解剖学や病理学など、基礎医学分野についても幅広く学習します。
また、実習では実際の医療現場に近い環境で技術を習得し、患者さんとのコミュニケーション能力も養われます。
歯科衛生士国家試験を受験する
養成機関を卒業すると、歯科衛生士国家試験の受験資格が得られます。国家試験は毎年3月に実施され、マークシート形式で行われます。
合格率は例年90%以上と高く、2025年(令和7年)の第34回歯科衛生士国家試験は91.0%でした。(参考:厚生労働省)
試験内容は以下のような分野から出題されます。
- 人体の構造と機能、疾病の成り立ち
- 歯・口腔の構造と機能
- 疾病の成り立ち、予防および回復の促進
- 歯科衛生士概論
- 臨床歯科医学
- 歯科予防処置論
- 歯科保健指導論
- 歯科診療補助論
試験後約1か月で合否が判明し、合格者には歯科衛生士免許が交付されます。
免許を取得し就職活動を開始する
国家試験に合格したら、厚生労働大臣の歯科衛生士名簿に登録され、免許証の交付を受けます。この免許取得により、歯科衛生士として正式に働けるようになります。
就職活動のタイミングと進め方は以下の通りです。
- 最終学年の春(4月~6月):情報収集開始、求人説明会参加
- 夏(7月~8月):見学やインターンシップ参加
- 秋(9月~12月):応募と面接
- 国家試験後(3月下旬):合格発表後に本格的な就職活動開始
就職後も継続的な学習とスキルアップにより、認定歯科衛生士の資格取得やキャリアアップを目指せます。
歯科衛生士の具体的な仕事内容

歯科衛生士の業務は法律で定められた専門性の高い国家資格業務として、口腔の健康を守るために幅広い役割を担っています。
歯科衛生士法に基づき、主に3つの専門業務を中心とした多岐にわたる仕事内容があります。ここでは、具体的な業務内容について詳しく解説します。
歯科予防処置:口腔の健康を守る専門業務
歯科予防処置は、歯科衛生士法で定められた歯科衛生士の重要な専門業務です。
虫歯や歯周病の発症を未然に防ぐための処置を行い、患者さんの口腔健康の維持・向上を図ります。主な歯科予防処置は以下の通りです。
- 歯垢・歯石の除去(スケーリング)
- 歯面清掃・研磨(PMTC)
- フッ化物歯面塗布
- シーラント(小窩裂溝填塞)
- 歯肉縁上の付着物・沈着物の機械的除去
定期的なメンテナンスにより、患者さんの口腔内環境を良好に保ち、将来的な歯の喪失を防ぐ重要な役割を担います。
歯科予防処置は歯科衛生士のみが行える業務のため、高い専門性と技術が必要です。
歯科診療補助:歯科医師をサポートする協働業務
歯科診療補助は、歯科医師の指示のもとで行う診療補助業務です。
診療がスムーズに進むよう医師をサポートし、患者さんの負担軽減にも貢献します。主な歯科診療補助業務は以下の通りです。
- 診療器具の準備・受け渡し
- バキューム操作による唾液・水分の吸引
- 患者さんへの説明・心理的サポート
- 概形印象採得
- 充塡物の研磨
- ホワイトニング処置
- 歯周ポケット検査・薬物塗布
歯科診療補助では、歯科医師との連携が極めて重要です。治療の流れを理解し、先回りして動く能力が求められます。
特に歯科に対して不安や恐怖心を抱える患者さんには、適切な言葉遣いでの説明や対話を通じて安心感を提供する役割も担います。
診療補助は歯科医師と歯科衛生士が協力して行う業務のため、高いコミュニケーション能力と臨機応変な対応力が必要です。
歯科保健指導:予防のための教育・指導業務
歯科保健指導は、患者さんが自分自身で適切な口腔ケアを行えるよう指導する業務です。
生活習慣の改善を含めた包括的なアプローチにより、口腔の健康維持をサポートします。主な歯科保健指導の内容は以下の通りです。
- ブラッシング指導(歯ブラシ・フロスの使用法)
- 食事・栄養指導
- 間食に関する指導
- 生活習慣の改善アドバイス
- 歯間ブラシの選択・使用法指導
- 義歯のお手入れ指導
歯科保健指導では、患者さん一人ひとりの口腔状態やライフスタイルに合わせた個別指導が重要です。
年齢層や生活環境によって異なるニーズに対応するため、小児から高齢者まで幅広い世代への指導技術が求められます。
まとめ
歯科衛生士は、全国どこでも働ける国家資格で、求人数が非常に多く安定したキャリアを築けます。ワークライフバランスが良く、結婚や出産後も復職しやすい点が魅力です。
専門性が高く、やりがいや社会貢献も実感でき、給与やキャリアアップの機会も期待できます。
東京都目黒区に位置するスガノ歯科クリニックでは、歯科衛生士を募集中です。免許があれば未経験・ブランクOKで、ホワイトニングコーディネーター有資格者歓迎の環境です。
JR山手線「目黒駅」よりバス5分の立地で通勤手当も支給、衛生士業務に加え受付・院内清掃・器具滅菌なども担当していただきます。
歯科衛生士として働きたい方は、ぜひこちらからご応募ください。


